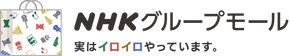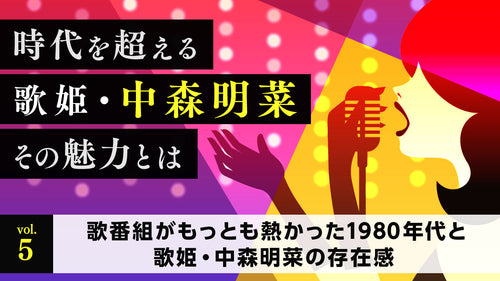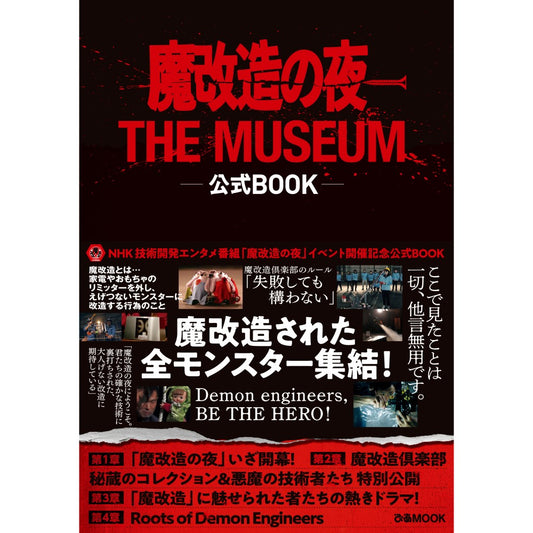| 音楽評論家・スージー鈴木による短期連載「80年代女性アイドルの聴き方」。全5回シリーズで、伝説の女性アイドルたちについて、主に音楽的視点から、その魅力に迫ります。 |
この短期連載、松田聖子、中森明菜、小泉今日子と来て、次におニャン子クラブとなると、意外に思われる方もいるでしょう。一部には、少しばかりの違和感を持たれる方すら、いらっしゃるかもしれません。
ただ、チャートアクションだけを見ると、80年代後半の一時期、ソロも含めた「おニャン子系」の楽曲が、上位をずっと占拠したのもれっきとした事実でして、だから少なくとも、「80年代女性アイドル」を語る上で、無視はできないのです。
「ポップの復権」―― 色眼鏡で見られがちな彼女たちの音楽を、先入観抜きで見つめると、ポップ、ポップス、ポップ・ミュージックの復権だった、だからこそ、あれだけ大きな支持を得られたのかと合点がいくのです。ちょっと詳しく説明しますね。
おニャン子クラブを生み出したフジテレビ系の番組『夕やけニャンニャン』の放送が始まったのは、85年4月でした。85年、つまり80年代の折り返し地点における女性アイドル界は、どんな景色だったか。
松田聖子は神田正輝と結婚し、それまでの実にきらびやかだったアイドル人生を中締めします。対して中森明菜は『ミ・アモーレ』でアダルトな世界を確立、日本レコード大賞に輝く。また小泉今日子は『なんてったってアイドル』で、アイドル界そのものをパロディ化する。
何が言いたいかというと、あれほど賑やかだった女性アイドル界が、突如空洞化したということ。そんな中、シンプルでキャッチーで、つまりはポップな音楽を伴って、空洞化したアイドル界を埋め合わせ、受け継いでいったのが、おニャン子の一群だったということです。
具体的にいえば、まずはトラッドなポップス系。代表曲は新田恵利『冬のオペラグラス』と福永恵規『風のInvitation』、おニャン子クラブ名義の『じゃあね』(3曲とも86年)。特に『冬のオペラグラス』は、フィル・スペクターやビーチ・ボーイズの要素を上手く使った、実に上品な仕立てのポップスになっています。
ちなみにこれら3曲とも、作詞はすべて秋元康。といいましょうか、以下のおニャン子系の全てが、秋元康の作詞。つまりおニャン子を語ることは、秋元康を語ることに他なりません。
ハードなロック系でいえば、うしろゆびさされ組の『うしろゆびさされ組』(85年)。高井麻巳子と岩井由紀子のユニットによるデビュー曲は、ディストーション・ギターがぎんぎん響くロックチューン。彼女たちの楽曲は、日本を代表するベーシストだった後藤次利の貢献もあり、ロックでファンキーな色合いが強いものが多かったのです。
ヨーロピアンなエレガント系としては、河合その子の『青いスタスィオン』(86年)を推します。こちらも後藤次利作品(後に河合と結婚)。ドラマティックな歌詞と質感の高いサウンドは、もっと評価されていいと思います(前回取り上げた『夜明けのMEW』に極まる、85~86年あたりの秋元康の歌詞も同様に、正当な評価が求められるところでしょう)。
おニャン子系=トラッドなポップス系、ハードなロック系、ヨーロピアンなエレガント系――つまりはシンプルでキャッチーで、ポップだった。メンバーのルックスや、メディア的仕掛けだけではない、これらの音楽的要素も、若者男子がおニャン子系に飛び付いた理由だったのです。
と、ここまで彼女たちの音楽について、色眼鏡で見られがちな現状とバランスを取るべく、かなりポジティブに推してみました。ただ、決定的な弱点があったとすれば、あまりに短命だったこと。
87年には解散、同時に『夕やけニャンニャン』も終了。ただ、ブームの渦中(のちょっと外れ)にいた私は、決して早過ぎるとは思いませんでした。それくらい、特に87年に入ったあたりからの「失速感」が強かったのです。
具体的にいえば、先に上げたような「ポップの復権」として推せる楽曲が少なくなった。あまりに大量かつ連続的に楽曲が量産された結果、個々の質の検証ができなくなり、正直「濫造」という印象を受けた。それが失速感につながっていった――。
ちなみに中森明菜と、おニャン子系の中でも最も企画性・素人性の高い「ニャンギラス」(立見里歌、樹原亜紀、名越美香、白石麻子)が同じレコード会社所属だったことにまつわるエピソードについて「音楽関係者」の発言。
――「明菜さんは、テレビ局の歌番組で『ニャンギラス』と居合わせた際、担当のワーナーの社員に対して『自分たちが世界の3大レーベルにいるという自負はないの? 恥ずかしくないの?』と、強い口調で叱責していました」(『SMART FLASH』/2022年11月22日)
企画性・素人性を打ち出すことは、秋元康ら「仕掛人」たちの目論見だったのでしょうが、もし、例えば山本彩(元・AKB48/NMB48)や、生田絵梨花(元・乃木坂46)のような音楽的才能がおニャン子クラブにもいて、かつ、その才能を引き出し、尊重する志向がマネジメント側にあれば、おニャン子系はもっと存続して、ポップをもっと復権し続けたのではないかと考えるのです。
それでも、先に挙げた作品のクオリティは、いつまでも色褪せることはありません。そのあたりをぜひ色眼鏡を捨て、オペラグラスで拡大しながら見て、いや聴いていただきたいと思うのです。
◆ライター

スージー鈴木
音楽評論家、小説家、ラジオDJ。1966年11月26日、大阪府東大阪市生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業。音楽評論家として、昭和歌謡から最新ヒット曲までを「プロ・リスナー」的に評論。bayfm『9の音粋』月曜日担当DJ。著書に『桑田佳祐論』『サザンオールスターズ1978-1985』(新潮新書)、『EPICソニーとその時代』(集英社新書)、『平成Jポップと令和歌謡』『80年代音楽解体新書』『1979年の歌謡曲』(いずれも彩流社)、『恋するラジオ』『チェッカーズの音楽とその時代』(いずれもブックマン社)など多数。