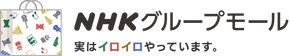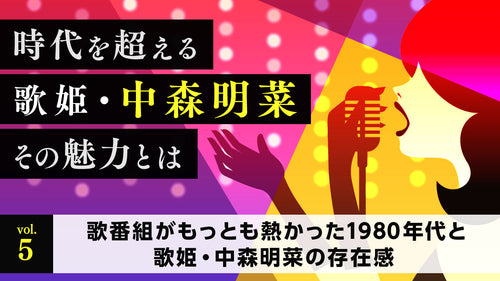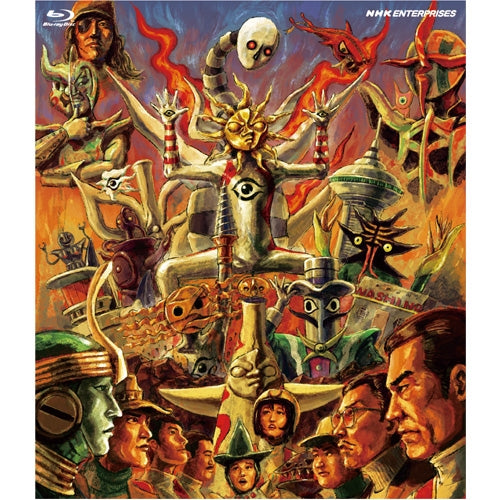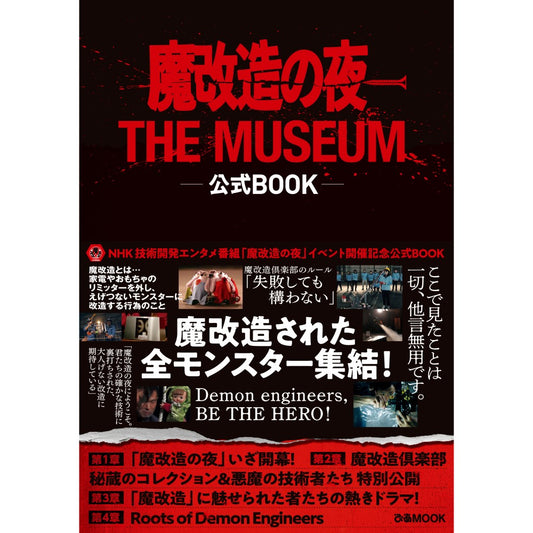| 年末の風物詩でもある「NHK紅白歌合戦」には、これまで数多くの歌手、アイドルが出場してきました。
ひとつの転換期ともいえる1980年の紅白歌合戦(第31回 NHK紅白歌合戦)では、松田聖子が「青い珊瑚礁」で初出場。田原俊彦は、“たのきんトリオ”の仲間、近藤真彦、野村義男に応援されて「哀愁でいと」を歌うなど、アイドル時代突入を感じさせました。 そこで今回は「80年代女性アイドルの聴き方」と題して、全5回シリーズで、伝説の女性アイドルたちについて、主に音楽的視点から、その魅力に迫っていきたいと思います。 ナビゲーターは「日本最後のロックンロール・バンドとしてのチェッカーズ」でもおなじみ、音楽評論家のスージー鈴木。 |
記念すべき第1回は、この方から始めざるを得ないでしょう。そうです――松田聖子。果たして、松田聖子が歌い・演じた音楽の魅力の本質とは何だったのか?
松田聖子のディスコグラフィを見て、いつも深く感じ入るのが、デビュー曲『裸足の季節』のリリース日が「1980年4月1日」という事実。
80年の春、新学期が始まる日、つまりは「80年代」という新しいディケイドの誕生日――それは、80年代女性アイドル界を代表する存在になるために仕組まれたリリース日のように、私には見えます。
では80年代、特にその前半に、日本の若者が見つめる日常の景色をカラフルに彩ったと言える松田聖子の音楽の魅力とは何か。まず挙げられるのは、「ニューミュージックの総括」とでも言うべき豪華な作家陣の存在です。
「ニューミュージック」はもはや死語ですが、意味するところは、この日本において、戦後生まれの若者たちが、ビートルズなどの洋楽の影響を受けて生み出した、歌謡曲とは一線を画す自作自演音楽の総称。
作詞家・松本隆を中心に、集まった腕利きの音楽家たち――松任谷由実(呉田軽穂名義)、大瀧詠一、細野晴臣、尾崎亜美、財津和夫、佐野元春(Holland Rose名義)……。
当時の松田聖子作品を聴いて感じるのは、これら腕利き音楽家たちが、松田聖子というメディアを通して、日本の音楽シーンを、もっと明るく爽やかで、かつ高品質なものにしたいという、ある種啓蒙的な意志です。
70年代末に、歌謡界とニューミュージック界がガチンコでぶつかった。そして80年代に入って、松田聖子という、あくまで歌謡曲のアイドルという「体制」に、松本隆の先導の下、ニューミュージック軍団がするすると入り込み、その内部から起こした音楽革命――。
とりわけ細野晴臣の手による『ガラスの林檎』『天国のキッス』など、極めて実験的でラディカルな作品が、松田聖子の名の下に大ヒットしたという事実が、日本の音楽シーンに及ぼした影響は、とても大きなものがあると考えます。
音楽的魅力として、次に挙げられるのが、その松本隆による歌詞の世界です。
実は、デビュー曲『裸足の季節』(80年)から5枚目の『夏の扉』(81年)までの作詞は、三浦徳子が担当していたのですが(最近では、あの松原みき『真夜中のドア~Stay with me』の作詞家として名高い)、6枚目の『白いパラソル』からは松本隆が担当します。
70年代までの歌謡曲や演歌における、女々しくて湿っぽく、男にかしずく「おんな」の世界を、大きく変革したのは、作詞家・阿久悠です。男と対等なまま別れていく尾崎紀世彦『また逢う日まで』(71年)に見られるように、阿久悠が描いたのは、自分の意志を持った強い「女性」でした。
それを継ぐように松本隆は、松田聖子作品において、同じく自分の意志を持ちながら、それでも肩をいからせず、明るくポジティブな「女の子」を描く。もちろんそれは、松田聖子本人のキャラクターと強くシンクロします。
「♪嘘よ 本気よ」「♪好きよ 嫌いよ」――気持ちの定まらない女の子の内面をありのままに表明しながら「あなた」を戸惑わせる『小麦色のマーメイド』(82年)などは、そんな松本隆の真骨頂と言えましょう。
ですが、松田聖子の最大の魅力として私が挙げたいのは、歌唱力です。
デビュー後すぐにブレイクするも、「ぶりっこ」「嘘泣き」などの言説で取り上げられたことで、ボーカリスト・松田聖子の凄みはほとんど語られなかった。また、未だに、その凄みに気付かないままの人が少なくないようにも思われます。何ともったいないことでしょう――。
なんて当てこすりを言いたくなるくらい、ボーカリスト・松田聖子の力量は素晴らしい。そんな松田聖子のボーカルについて、私が最も推したいのは、初期の初期です。先述べた三浦徳子時代、『裸足の季節』から『夏の扉』まで。
その三浦徳子は、後にこう語っています――「とにかく声量がありましたね。スタジオで彼女の歌をはじめて聴いたとき、いくらでも声が出るんで驚きました。マイクなんかいらないくらいで、今現在の声とは全く違っていたんじゃないでしょうか」(1995年『月刊カドカワ』7月号)
シングル『チェリーブラッサム』(81年)に加えて、おすすめしたいのはデビューアルバムの『SQUALL』(80年)。特にタイトルチューンの『SQUALL』や『ロックンロール・デイドリーム』のボーカルは、歌うというより、(勢い余った表現ですが)「吠えている」という感じ。何度聴いてもほれぼれします。
1980年、「ぶりっこ」「嘘泣き」などと揶揄(やゆ)されながらも、その1人の「女の子」は、我関せずとマイクの前で歌った、吠えた!――そのとき、80年代が始まったのです。
◆関連商品
松田聖子 聖子スイート・コレクション~80’sヒッツ CD-BOX 全5枚セット【NHKスクエア】 
◆ライター

スージー鈴木
音楽評論家、小説家、ラジオDJ。1966年11月26日、大阪府東大阪市生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業。音楽評論家として、昭和歌謡から最新ヒット曲までを「プロ・リスナー」的に評論。bayfm『9の音粋』月曜日担当DJ。著書に『桑田佳祐論』『サザンオールスターズ1978-1985』(新潮新書)、『EPICソニーとその時代』(集英社新書)、『平成Jポップと令和歌謡』『80年代音楽解体新書』『1979年の歌謡曲』(いずれも彩流社)、『恋するラジオ』『チェッカーズの音楽とその時代』(いずれもブックマン社)など多数。